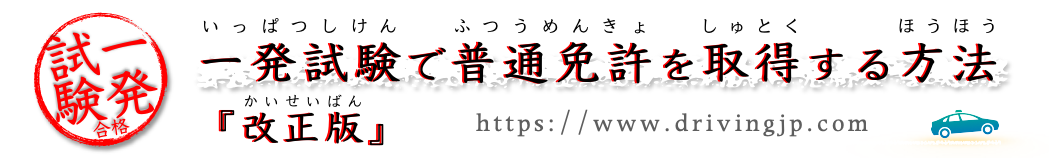後期高齢者講習(75歳以上)を安心して迎えるために

安全と安心を守る、これからの運転ライフを考える
これからの「安全運転ライフ」を見つめ直す機会
75歳以上になると、自動車免許の更新時に「後期高齢者講習」を受けることが義務づけられています。これは単なる試験ではなく、これからも安全に運転を続けるためのサポートとして行われる大切な機会です。
高齢になると、どうしても判断力や反応速度、視力の低下など、若い頃にはなかった変化が現れてきます。
しかし、これを「できなくなる」サインではなく、「より安全に運転を続けるためのチェック」として前向きにとらえることが大切です。
家族や周囲の方々も、この講習を通じて「今後の運転をどう続けるか」「運転以外の移動手段をどう活用していくか」を一緒に考えるきっかけにしましょう。
■ 後期高齢者講習を受けられる期間とは?
免許の有効期限が近づくと、警察から「講習のお知らせ(高齢者講習通知書)」が届きます。
通知が届いたら、講習を受けられる期間を確認しましょう。
後期高齢者講習は、誕生日の6か月前から受講可能です。
たとえば誕生日が8月の方は、2月から受講できます。
早めに予約することで、混雑を避けてスムーズに受講することができます。
なお、講習は免許更新のために必ず受講が必要です。
もし受けないまま有効期限を過ぎてしまうと、免許は失効してしまうため注意しましょう。
■ 後期高齢者講習の予約方法
講習の予約は、通知書に記載された指定の教習所や運転免許センターで行います。
電話予約が基本ですが、地域によってはインターネット予約ができる場合もあります。
人気の講習日程はすぐに埋まってしまうため、通知が届いたらできるだけ早めに予約を入れましょう。
また、講習は受講日時だけでなく「どのタイプの講習になるか」も通知書に記載されています。
事前に内容を確認しておくと、当日も安心です。
■ 後期高齢者講習の内容と種類
75歳以上のドライバーが受ける講習は、主に次の2種類に分かれます。
① 一般講習
記憶力・判断力の検査結果が良好だった方が対象。
内容は以下の通りです。
-
運転に関する講義(安全運転に関する知識や注意点)
-
実車による運転技能の確認(教習車での走行)
講習時間は約2時間半ほどで、これまでの運転を振り返りながら改善点を学ぶことができます。
② 高齢者講習(認知機能検査付き)
記憶力・判断力の検査結果により、より丁寧な確認が必要とされた方が対象。
内容は一般講習に加えて、個別の助言や指導が行われます。
講師が運転状況を細かくチェックし、「この動作を少し変えるともっと安全になります」といった前向きなアドバイスをしてくれます。
どちらの講習も“試験”ではなく“サポート”が目的です。
緊張せずに、安心して受講することが大切です。
■ 講習を受ける前にできる準備や対策
講習で慌てないために、次のような準備をしておくと安心です。
-
視力・聴力のチェック:眼鏡や補聴器を日常的に使う場合は、当日も必ず持参。
-
体調管理:寝不足や体調不良のまま受けると判断が鈍るため、前日はゆっくり休む。
-
運転のリハビリ:最近あまり運転していない方は、家族と一緒に短距離ドライブで感覚を戻しておく。
また、教習所では講師がとても丁寧に対応してくれます。
不安な点は遠慮せずに相談しましょう。
■ 家族や周囲の人ができるサポート
後期高齢者講習は、本人だけでなく家族にとっても大切なタイミングです。
「まだ運転できるのかな?」
「返納を勧めるのは失礼かな?」
そうした気持ちが出るのも自然なことです。
大切なのは、“本人の気持ちを尊重しながら寄り添う姿勢”です。
たとえば、
-
一緒に予約手続きを手伝う
-
当日の送迎をする
-
講習後に感想を聞く
こうした小さな関わりが、本人にとって大きな安心感になります。
■ 更新か返納か、前向きな選択を
後期高齢者講習の結果や内容を踏まえて、運転を続けるか、免許を返納するかを考える方もいます。
どちらを選ぶにしても、それは「自分や家族の安全を守るための前向きな決断」です。
免許を返納しても、自治体によってはバスやタクシーの割引制度や買い物支援サービスなどが用意されています。
また、「運転を続ける」場合でも、運転時間を短くしたり、夜間を避けたりと、より安全に楽しむ工夫が可能です。
■ まとめ:安全を続けるための第一歩
後期高齢者講習は、単なる義務ではなく、
「これからも安全に運転を楽しむための再確認の場」です。
高齢になっても、車があることで行動範囲は広がり、生活の質も保たれます。
講習を通じて、自分の運転を振り返り、新しい工夫を取り入れることで、より安全で快適なカーライフを続けていきましょう。