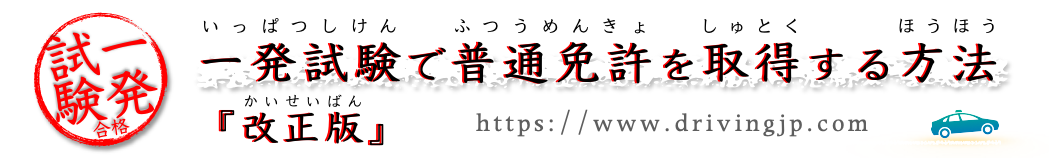「認知・判断・操作」で守る!

交通事故ゼロへの道
なぜ事故は起こる? その答えは“3つの行動”にある
なぜ事故は起こるのか
どれだけ注意していても、交通事故はゼロにはならない。
そう言われることがあります。
しかし、事故の多くは“偶然”ではなく、“原因”があります。
ブレーキが間に合わなかった、歩行者に気づかなかった、急な割り込みに反応できなかった……。
それらの背景には必ず、「認知」「判断」「操作」のいずれか、または複数の段階でのミスが潜んでいます。
安全運転の三原則と呼ばれるこの3つの要素は、実はすべてのドライバーが日常的に行っている行為です。
つまり、事故を防ぐカギは、この3つの質をいかに高めるかにあります。
事故の根本原因——「認知の遅れ」
最も多い事故の原因は、「認知」のミスです。
「認知」とは、周囲の状況を正確に把握すること。
前方の車間距離、信号の変化、歩行者や自転車の動きなど、運転中の情報は常に変化しています。
ところが、スマートフォンの操作や考え事、疲労などで注意が散漫になると、情報の一部を見落とすことがあります。
たとえば、わずか1秒の「見落とし」が、時速60kmでは約17メートルの距離を進むことに相当します。つまり、「ちょっと目を離しただけ」で、危険はすぐに目の前に現れるのです。
認知力を高めるには、「視野を広く持つ」意識が大切です。
焦点を一点に固定せず、ミラーや周囲の動きをこまめに確認する。
信号の先にある歩行者や対向車までを“予測”して見る。
これだけで事故のリスクは大幅に減少します。
「判断のズレ」が生む危険
状況を認知しても、その後の「判断」が誤れば危険は防げません。
「今なら右折できる」「もう少し行ける」「車間は十分あるだろう」
こうした瞬間の判断が事故を左右します。
人は自分の運転技術を過信しやすく、また「早く進みたい」「面倒を避けたい」といった心理が冷静な判断を狂わせることもあります。
判断の精度を高めるには、“安全マージン”を常に意識することです。
たとえば、「止まれる距離を保つ」「信号の変わり目では進まない」「右折時は相手の速度を見誤らない」など、慎重な選択を習慣づける。
迷ったときは「行かない」選択を取るのが、結果的に最も安全です。
正しい「操作」が命を守る
最後の要素が「操作」です。
たとえ認知も判断も正しくても、ブレーキやハンドル操作が遅れれば事故は防げません。
操作ミスの多くは、焦りや緊張、または操作に対する“慣れ”が原因です。
たとえば、「慌ててブレーキとアクセルを踏み間違える」「ハンドルを切りすぎて縁石に接触する」といった例は誰にでも起こり得ます。
操作技術を高めるには、「常に落ち着いて」「余裕を持つ」ことが基本です。
特に初心者やペーパードライバーは、急ブレーキ・急ハンドルを避け、一定のリズムで運転する意識を持ちましょう。
また、定期的に車両感覚を再確認する練習(駐車・車庫入れ・バック走行など)も有効です。
事故を防ぐための3つの習慣
安全運転の三原則を日常で生かすには、以下の3つの習慣が効果的です。
-
「予測運転」を心がける
目の前の動きだけでなく、「次に何が起こるか」を常に想像する。
子どもが歩道にいたら「飛び出すかもしれない」、車が減速したら「右折するかもしれない」。
予測することで反応の遅れを防げます。 -
「心の余裕」を持つ
焦りは判断を鈍らせ、怒りは操作を乱します。
イライラした時ほど深呼吸し、スピードを落とす。精神的な余裕が、身体の動きを安定させます。 -
「点検と確認」を怠らない
運転前の車両点検、乗車時のミラー・シート調整、発進時の安全確認。
当たり前のルーティンこそが、安全運転の土台です。
安全運転は「技術」より「意識」
「認知・判断・操作」は、単なる技術ではなく“意識の姿勢”です。
車を運転するたび、ドライバーは命を預かっています。
その重みを自覚し、一つひとつの行動を丁寧に行うことで、事故は必ず減らせます。
ハンドルを握る手に「思いやり」を。
視線の先に「未来」を見ること。
それこそが、真の安全運転の第一歩です。